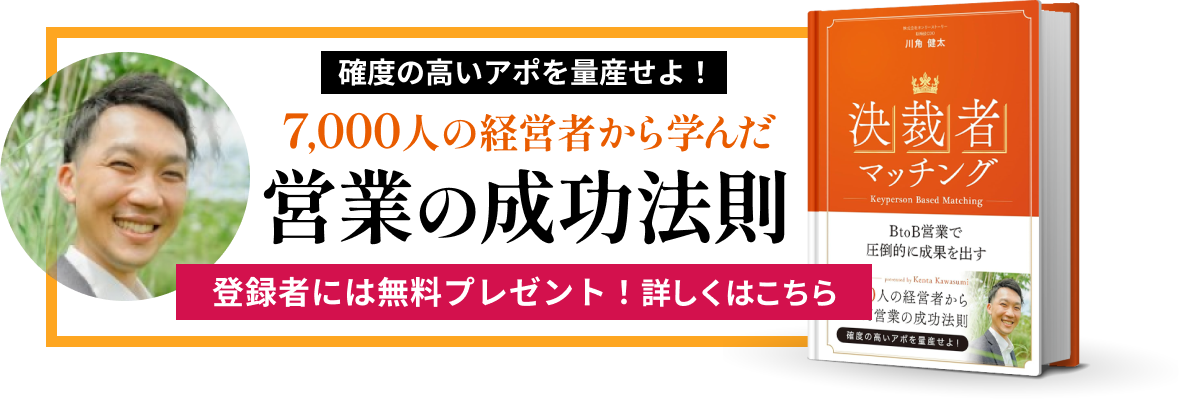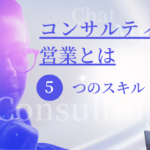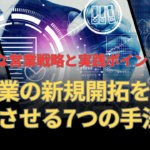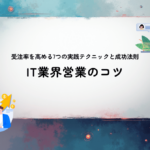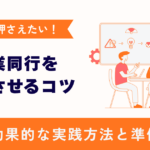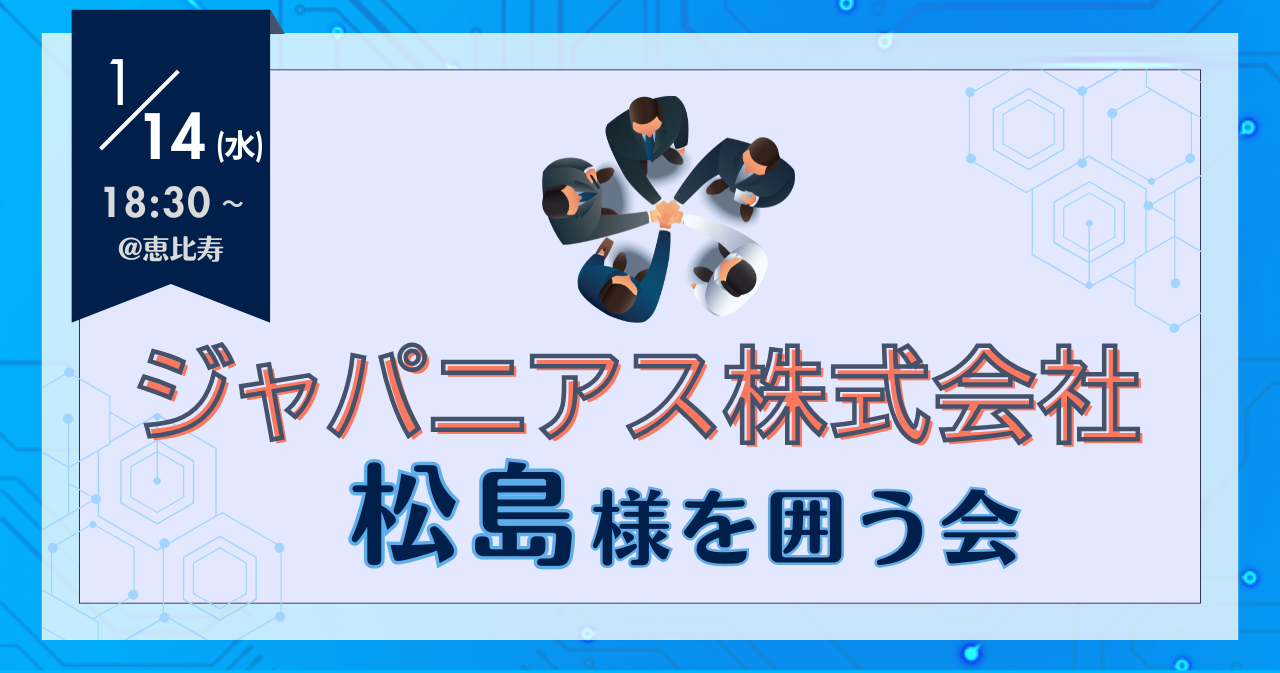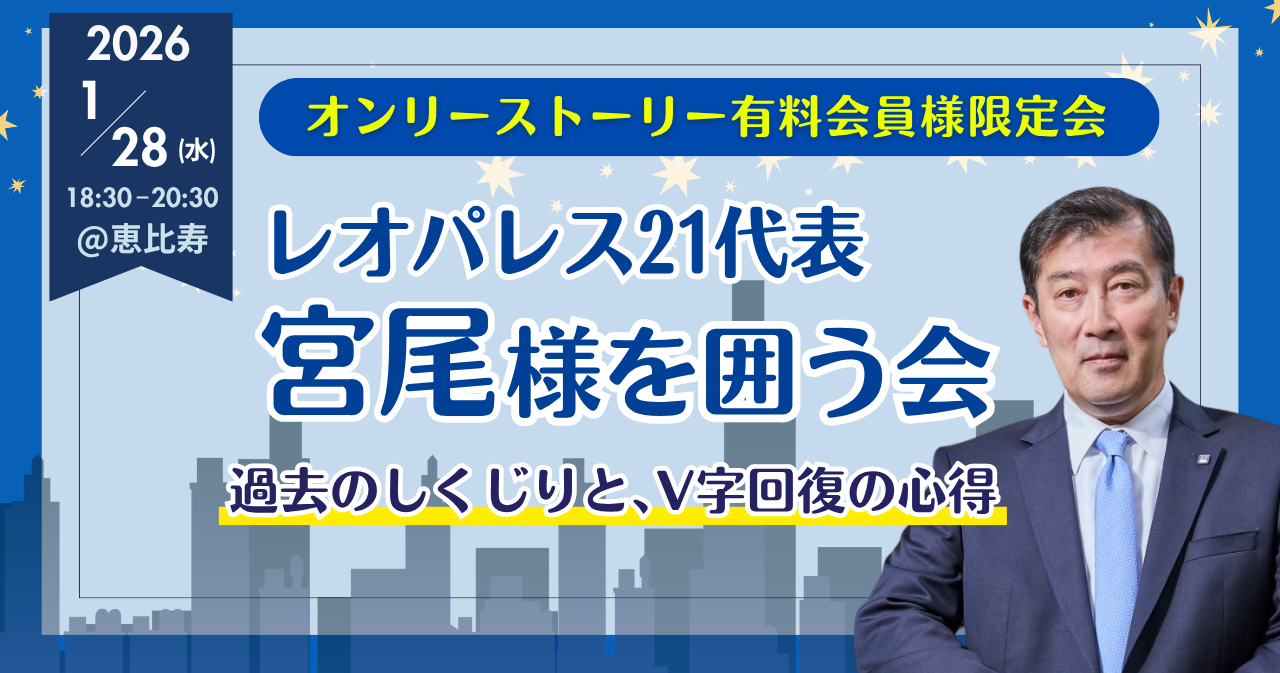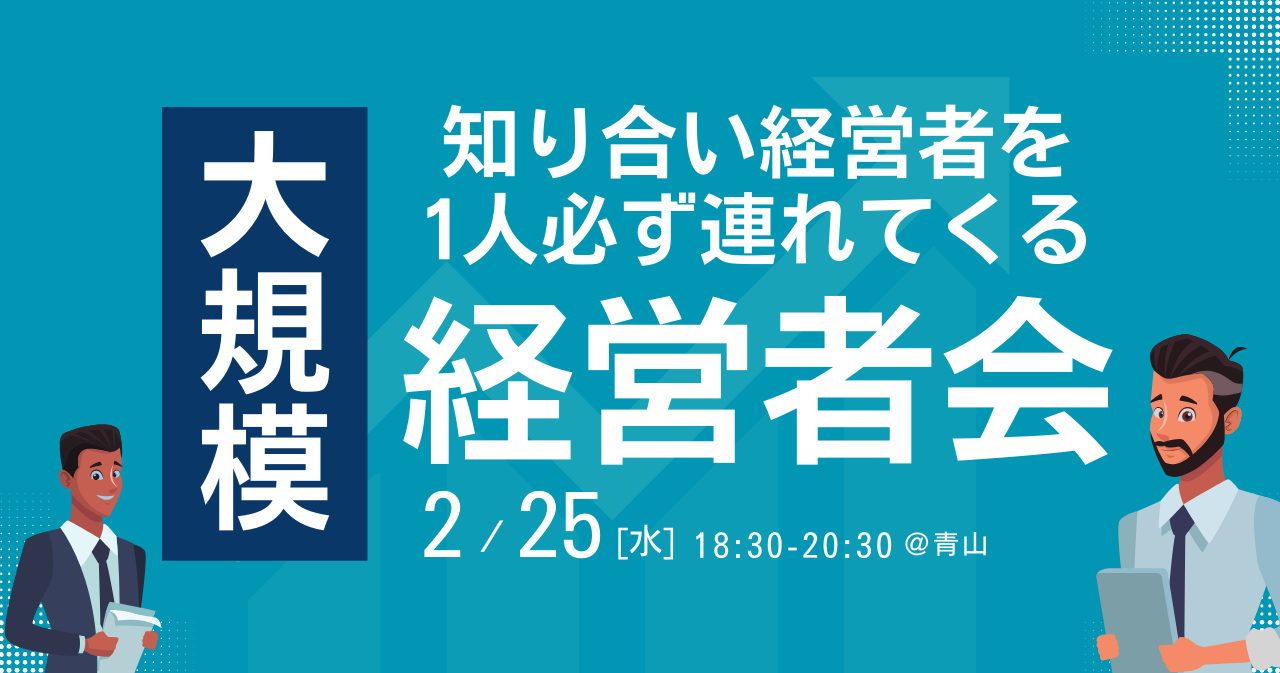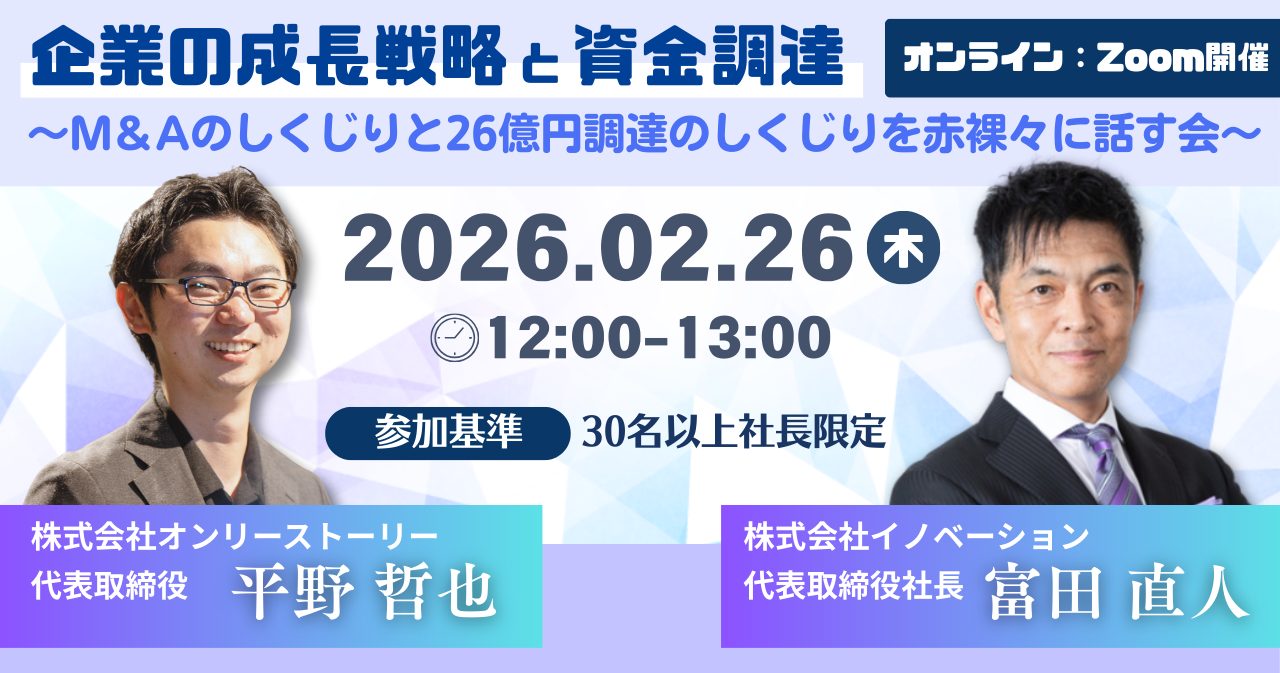「エース営業が退職した途端、ぱったりと新規の問い合わせが止まってしまった…」
「Web広告費をかけ続けないとリードがゼロになる。このままの自転車操業で大丈夫だろうか…」
「展示会やテレアポなど、場当たり的な施策ばかりで、安定した見込み客の獲得ができない…」
BtoBビジネスにおいて、このような「属人化」した、「場当たり的」なリード獲得活動に限界を感じていませんか。
この記事では、数多くの企業のマーケティング・営業組織の立ち上げを支援してきたプロの視点から、安定的・継続的にリードを獲得し続けるための「仕組み」の作り方を、誰にでも実践できるよう5つのステップに沿って体系的に解説します。
この記事を最後まで読めば、再現性の高いリード獲得の全体像から、具体的な構築手順、必要なツールまで、あなたの会社を成長軌道に乗せるための設計図がすべて手に入ります。
そもそも「リード獲得の仕組み」とは?単発の施策との決定的な違い
「リード獲得の仕組み」という言葉を耳にする機会は増えましたが、その本質を正しく理解できているでしょうか。
単発の施策を繰り返すこととの違いを明確にすることで、目指すべきゴールの全体像がはっきりと見えてきます。
リード獲得の仕組みの定義:再現性のある「集客から育成までの流れ」
リード獲得の仕組みとは、単に展示会に一度出展したり、Web広告を一度配信したりといった、単発の施策のことではありません。
それは、複数のオンライン・オフライン施策が有機的に連動し、継続的かつ半自動的に見込み客(リード)を生み出し、そのリードの興味関心を育成(ナーチャリング)し、購買意欲が高まった段階で営業部門へと引き渡すまでの一連のシステム全体を指します。
つまり、個人のスキルやその時々の頑張りに依存せず、誰がやっても一定の成果を出せる「再現性」があること、それが単なる施策との決定的な違いです。
仕組み化がもたらす3つの経営メリット
リード獲得を仕組み化することは、企業経営に計り知れないメリットをもたらします。
第一に、「営業活動の安定化と売上予測の精度向上」です。
毎月安定した数の質の高いリードが供給されるため、営業活動が計画的に行え、売上予測のブレが少なくなります。
第二に、「属人性の排除と組織力の向上」です。
特定の個人のスキルに依存しないため、エース社員の退職リスクに強く、組織全体の営業力が底上げされます。
そして第三に、「マーケティング・営業活動の費用対効果(ROI)の最大化」です。
各施策の成果がデータで可視化されるため、効果の高い施策に投資を集中させ、無駄なコストを削減することができます。
全体像の要「マーケティングファネル」を理解する
この仕組みを設計する上で核となる考え方が、「マーケティングファネル」です。
これは、顧客があなたの商品やサービスを認知し、最終的に購入に至るまでの心理プロセスを、漏斗(ファネル)の形で表現したものです。
一般的に、①自社の存在を知る「認知」段階、②商品やサービスに興味を持つ「興味・関心」段階、③他社製品と比較する「比較・検討」段階の3つに分けられます。
リード獲得の仕組みとは、この各ファネル段階にいる潜在顧客に対して、それぞれ最適なアプローチを行い、スムーズに次の段階へと引き上げていくための緻密なコミュニケーション設計そのものなのです。
【5ステップで構築】BtoBリード獲得の仕組みの作り方
それでは、実際にリード獲得の仕組みを構築するための、具体的な5つのステップを解説していきます。
このステップに沿って一つずつ進めていくことで、誰でも自社に最適化された、強力なリード獲得の仕組みを設計することが可能です。
ステップ①:ターゲット顧客(ペルソナ)を明確に定義する
仕組み作りの全ての土台となるのが、「誰に」アプローチするのかを明確に定義することです。
ターゲットが曖昧なままでは、どんな施策も的外れになってしまいます。
まずは、自社にとって最も価値のある理想の顧客企業像(ICP:Ideal Customer Profile)を、業種、企業規模、抱えている課題といった観点から定義します。
次に、その企業の中で実際にアプローチすべき担当者像(ペ-ルソナ)を、役職、年齢、情報収集の方法、業務上の悩みといったレベルまで、具体的に描き出します。
このペルソナが、後の全ての施策やコンテンツ制作における「判断のコンパス」となります。
ステップ②:カスタマージャーニーマップを作成し、顧客接点を洗い出す
ターゲット顧客(ペルソナ)を定義したら、次はそのペルソナが自社の製品やサービスを認知し、最終的に契約に至るまでの「旅(ジャーニー)」を可視化します。
これがカスタマージャーニーマップです。
「課題の認識」→「情報収集」→「比較検討」→「導入決定」といった各段階で、ペルソナがどのような思考や感情を抱き、どのような行動を取るのかを時系列で描き出します。
このプロセスを通じて、各段階で顧客がどのような情報に触れるのか、すなわち自社との「顧客接点(タッチポイント)」がどこにあるのかを洗い出すことができます。
このマップが、後の施策配置の設計図となります。
ステップ③:各ファネル段階に最適な「リード獲得施策」を配置する
カスタマージャーニーマップで洗い出した顧客接点と、マーケティングファネルの考え方を組み合わせ、各段階に最適なリード獲得施策を配置していきます。
例えば、まだ課題に気づいていない「認知」段階の顧客には、SEO対策を施したブログ記事やWeb広告で、まずは広く存在を知ってもらいます。
次に、情報収集を始めた「興味・関心」段階の顧客には、より専門的なホワイトペーパーやウェビナーを提供し、リード情報を獲得します。
そして、具体的な導入を考える「比較・検討」段階の顧客には、導入事例や製品資料、無料トライアルを提供し、購買意欲を最大限に高めます。
このように、顧客の検討度合いに応じた施策を戦略的に配置することが重要です。
ステップ④:リードを育成する「ナーチャリング」のシナリオを設計する
獲得したリードの多くは、すぐには商談や契約には至りません。
これらの「まだ温度感の低いリード」を放置せず、継続的なコミュニケーションを通じて信頼関係を築き、購買意欲を高めていくプロセスが「リードナーチャリング(育成)」です。
このナーチャリングこそ、仕組み化の肝となります。
例えば、MA(マーケティングオートメーション)ツールを活用し、獲得したリードに対して、彼らの興味関心に合わせたお役立ち情報をステップメールで自動配信するシナリオを設計します。
あるいは、インサイドセールス部門が定期的に電話で状況をヒアリングし、関係性を構築していくといった、人とツールを組み合わせたシナリオも有効です。
ステップ⑤:効果測定のための「KPI」を設定し、PDCAを回す
仕組みは一度作ったら終わりではありません。
市場や顧客の変化に合わせて、継続的に改善していく必要があります。
そのために不可欠なのが、各施策の成果を客観的に評価するための「KPI(重要業績評価指標)」の設定です。
例えば、「月間の新規リード獲得数」「リード1件あたりの獲得単価(CPL)」「リードから商談に繋がった割合(商談化率)」といったKPIを定めます。
そして、これらの数値をツールを使って定点観測し、目標に達していない部分があれば、その原因を分析し、改善策を実行する。
このPDCAサイクルを粘り強く回し続けることが、仕組みをより強力なものへと進化させていくのです。
リード獲得の仕組みを支える必須ツールと組織体制
ここまで解説してきた仕組みを実際に動かし、成果を最大化するためには、それを支えるための「武器(ツール)」と「チーム(組織体制)」が不可欠です。
ここでは、リード獲得の仕組みを構築・運用する上で、ほぼ必須となるツールと、理想的な組織体制について解説します。
ツールの三種の神器:MA・SFA/CRM・CMS
リード獲得の仕組みを効率的に運用するためには、3つのツールの連携が鍵となります。
一つ目は、リードの獲得と育成(ナーチャリング)を自動化する司令塔である「MA(マーケティングオートメーション)」。
二つ目は、営業部門が商談の進捗や顧客情報を一元管理するためのデータベースとなる「SFA/CRM」。
そして三つ目が、SEOやコンテンツマーケティングの母艦となるウェブサイトを構築・運用するための基盤である「CMS(コンテンツ管理システム)」です。
これらのツールがデータを連携させることで、マーケティング活動から営業活動まで、顧客の動きを分断なく追跡し、最適なアプローチを行うことが可能になります。
組織体制の鍵:「THE MODEL」型の分業体制
強力な仕組みを運用するためには、組織体制もそれに合わせて最適化する必要があります。
その理想的な形の一つが、セールスフォース社が提唱する「THE MODEL」型の分業体制です。
これは、顧客の購買プロセスに合わせて、①マーケティング(リード獲得)→②インサイドセールス(リード育成・商談化)→③フィールドセールス(商談・受注)→④カスタマーサクセス(契約後の成功支援)という4つの部門が、それぞれの専門性を持って連携するモデルです。
各部門が明確なKPIを追いかけることで、プロセス全体の効率が最大化され、リード獲得の仕組みがスムーズに機能するようになります。
リード獲得の仕組み作りでよくある失敗と、その乗り越え方
多くの企業がリード獲得の仕組み作りに挑戦しますが、残念ながら全ての企業が成功するわけではありません。
ここでは、仕組み作りにおいて陥りがちな3つの典型的な失敗パターンと、それを乗り越えるための対策を解説します。
失敗①:ターゲット設定が曖昧で、質の低いリードばかり集めてしまう
仕組み作りの最初のステップである「ターゲット設定」が曖昧なまま進んでしまうと、どんなに優れた施策を打っても、自社の製品やサービスに全く興味のない、質の低いリードばかりが集まってしまいます。
結果として、営業部門は確度の低いリードへの対応に疲弊し、マーケティング部門への不満が募るという悪循環に陥ります。
これを乗り越えるには、営業部門とマーケティング部門が共同で、理想の顧客像(ICP)とペルソナを徹底的に議論し、明確な定義を言語化して、組織全体の共通認識とすることが不可欠です。
失敗②:リードを獲得するだけで満足し、「育成」の視点が欠けている
ホワイトペーパーやウェビナーなどで多くのリード情報を獲得できたとしても、その後のフォローアップ、すなわち「ナーチャリング」の仕組みが設計されていなければ、そのほとんどは宝の持ち腐れとなってしまいます。
獲得したリードの9割は、すぐには顧客にならない「将来の見込み客」です。
この失敗を乗り越えるには、リードを獲得した後のコミュニケーションシナリオを事前に設計しておくことが重要です。
MAツールを活用したステップメールや、インサイドセールスによる定期的な電話フォローなど、継続的に関係性を構築し、顧客の検討度合いを高めていくプロセスを必ず組み込みましょう。
失敗③:マーケティング部門と営業部門の連携が取れていない(サイロ化)
リード獲得の仕組み作りにおいて、最も根深く、そして最も大きな失敗要因となるのが、マーケティング部門と営業部門の連携不足、いわゆる「サイロ化」です。
マーケティングは「リードの数」、営業は「受注の質」をそれぞれ追いかけるあまり、お互いの目標や活動内容を理解せず、協力関係が築けていない状態です。
この壁を乗り越えるためには、両部門共通の目標(例えば、売上金額や商談化数)を設定したり、定期的な情報交換の場(合同ミーティング)を設けたりすることが不可欠です。
「SLA(Service Level Agreement)」を結び、リードの質や対応ルールを明確に定義することも有効な手段です。
まとめ:リード獲得の仕組みとは、企業の「成長エンジン」そのものである
本記事では、BtoBビジネスにおけるリード獲得の仕組みを構築するための、全体像から具体的なステップ、そしてそれを支えるツールや組織までを網羅的に解説してきました。
安定したリード獲得の仕組みとは、顧客の購買プロセスを深く理解し、それに合わせた最適な施策を設計・連携させ、そしてデータに基づいて継続的に改善し続けることで構築されます。
そして、この仕組み化は、単なるマーケティングや営業活動の効率化に留まりません。
それは、企業の売上を継続的かつ安定的に生み出し続ける「成長エンジン」を、自社の内部に作り上げるという、極めて重要な経営戦略そのものなのです。
まずはこの記事で紹介した「ステップ①:ターゲット顧客の定義」から始めてみてください。
誰のためにこの仕組みを作るのかを徹底的に考えること。
それが、あなたの会社に強力な成長エンジンを構築するための、最も重要で、そして確実な設計図となります。