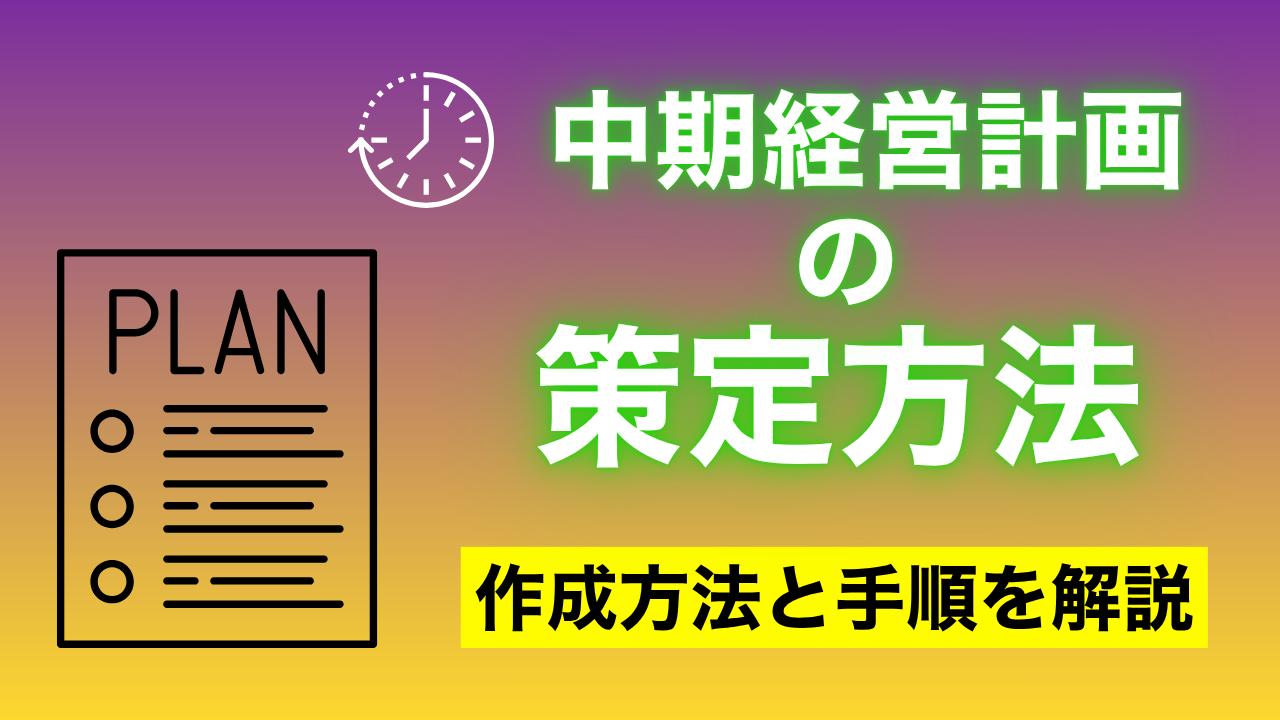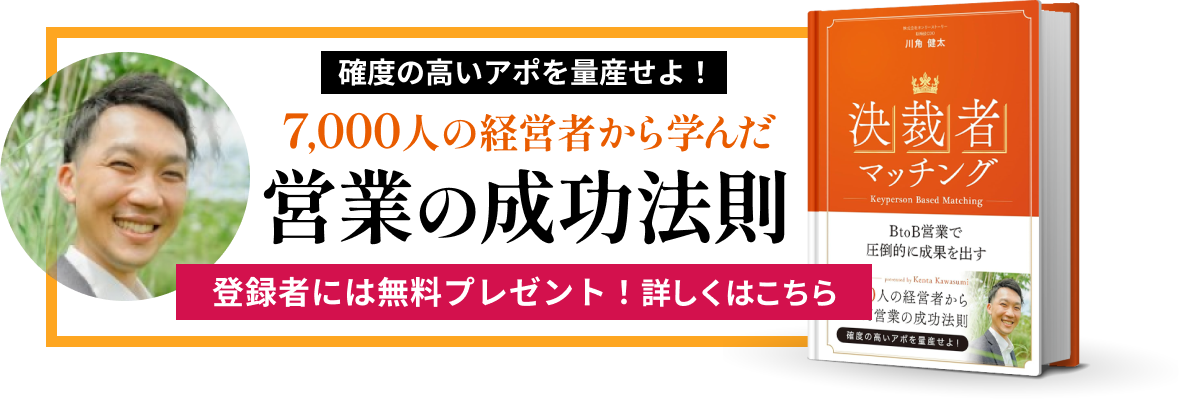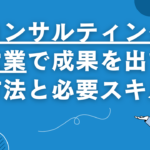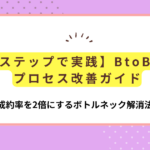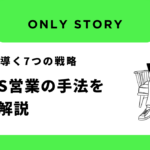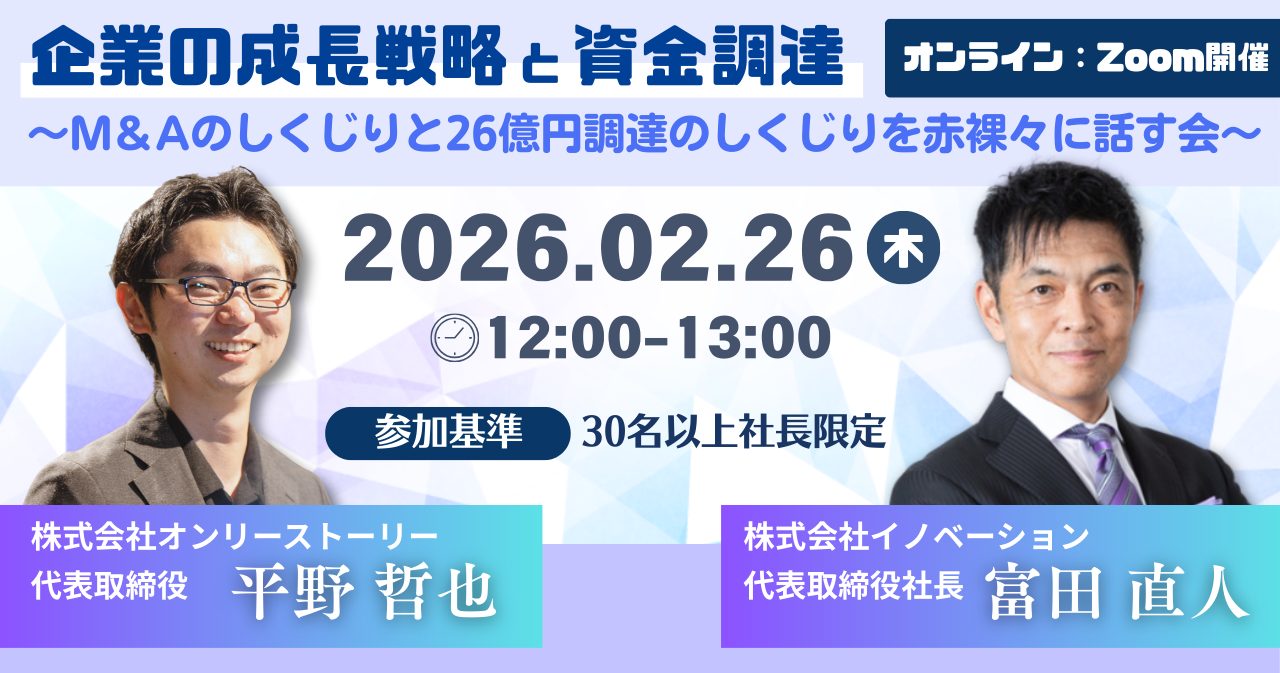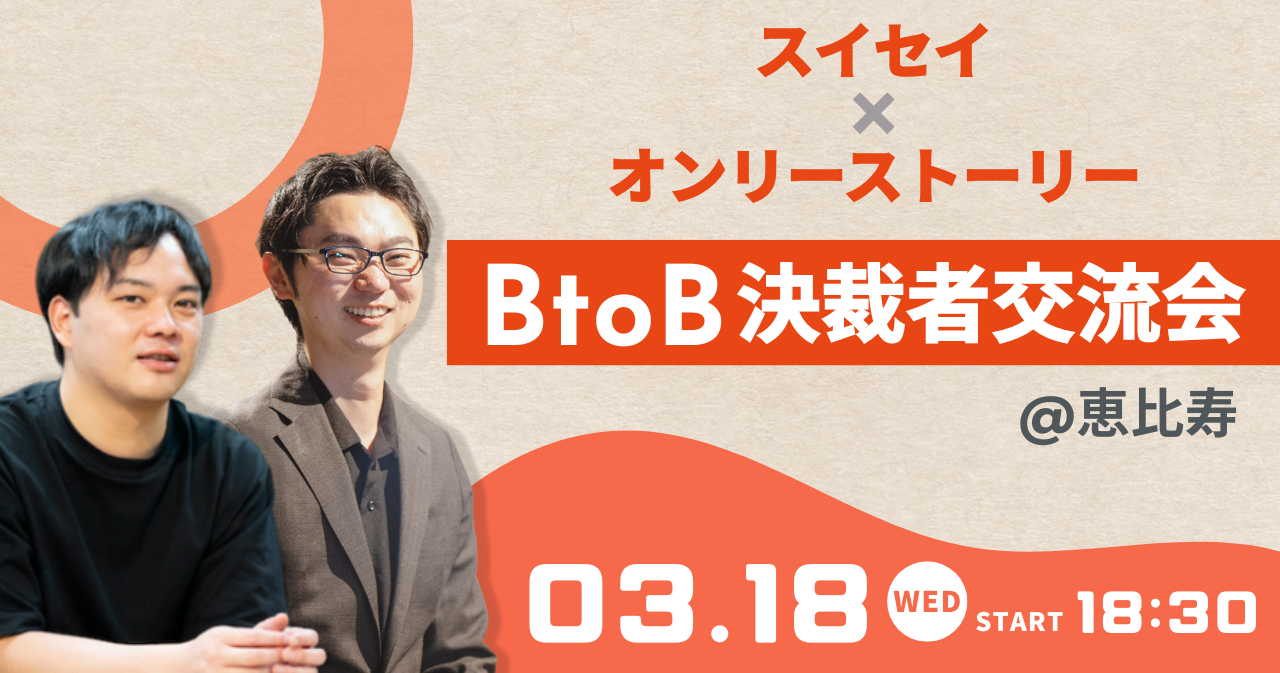中期経営計画とは
中期経営計画は、企業が向かうべき将来の姿と現在の状況とのギャップを埋めるための計画です。一般的には3年から5年のスパンで、経営方針や数値目標を具体的に示したものになります。
長期経営計画が5年から10年という大きな枠組みで企業のビジョンを描くのに対し、中期経営計画はその間の中間地点で、より実現可能性の高い具体的な戦略を示します。短期経営計画は1年単位の詳細な行動計画ですから、その三者は異なる役割を果たしながらも、互いに補完し合う関係にあるのです。
定義と基本的な考え方
中期経営計画の定義をシンプルに言うと、「企業が3~5年後のあるべき姿を定め、そこに到達するために必要な戦略と具体的な施策をまとめた計画」ということになります。
この計画の中には、売上目標や利益目標といった定量的な数値が含まれます。同時に、事業戦略の方向性や組織構造の改革、人材戦略といった定性的な要素も重要な位置を占めています。企業がただ利益を追求するのではなく、どのような価値を社会に提供し、どのようにビジネスモデルを進化させるのかまで含めて考えるものです。
期間設定が3~5年である理由
では、なぜ3~5年という期間が選ばれるのでしょうか。その理由は、経営環境の予測可能性と計画の実効性のバランスにあります。
10年先を完全に予測することは難しく、計画が陳腐化する可能性が高いです。一方で1年単位の短期計画だけでは、企業の大きな戦略転換に対応できません。3~5年というスパンなら、市場環境を合理的に予測でき、かつ組織全体で実行力を発揮できる期間として機能するのです。従業員にとっても、この期間は理解しやすく、モチベーションを維持しやすい期間だとされています。
長期経営計画・短期経営計画との違い
三つの経営計画は、それぞれ異なる役割を担っています。
長期経営計画は、企業が目指す最終的なビジョンや使命を描くもので、抽象度が高く理想的な目標を示します。これに対し、短期経営計画は今年度の具体的なアクションプランで、各部門や個人レベルまで落とし込まれた詳細な計画です。
中期経営計画はその中間に位置し、長期ビジョンを短期計画に変換するための「橋渡し」的な役割を果たします。つまり、中期経営計画があるからこそ、長期的な理想と短期的な現実のズレを最小化できるということです。
中期経営計画の策定が重要である理由
企業経営にとって中期経営計画の策定が重要とされているのは、いくつかの具体的な理由があります。
経営方針の明確化とビジョン共有
中期経営計画を策定するプロセスを通じて、経営トップの想いが具体化されます。最初は頭の中にあったぼんやりとした理想像が、言葉や数字に置き換わることで初めて現実味を帯びるのです。
この過程で経営方針が明確になると、従業員全体で目指す方向性を共有することができます。口頭説明だけでは伝わりきらないニュアンスも、計画書として可視化することで、社員の理解度が格段に上がるのです。全員がおなじ方向を向くことで、組織のシナジーが生まれやすくなります。
企業の持続的成長を実現する機能
短期的な利益追求だけに目がいっていると、中長期的な競争力を失うことがあります。中期経営計画は、今期の数字だけでなく、3年後、5年後の企業が何をすべきかを示すことで、持続的な成長の道筋を作り出します。
例えば、今年度は赤字になるかもしれませんが、中期的には黒字化を達成できるという見通しを立てることができます。こうした計画があれば、短期的な困難に直面しても、企業全体で乗り越える動機が生まれるのです。
ステークホルダーとの信頼構築
銀行などの金融機関から融資を受ける際、しっかりした中期経営計画は強力な説得材料になります。同様に、投資家や取引先、従業員に対しても、企業の将来性を説明する時に大いに役立ちます。
計画の背景にある現状分析が充実していて、戦略が明確なら、相手方の信頼度は大きく高まるのです。特に昨今のESG投資の拡大に伴い、企業のビジョンや持続可能性への取り組みを示す重要なツールになっています。
中期経営計画を策定するメリット
中期経営計画の策定には、企業にとって多くの実質的なメリットがもたらされます。
自社の現状と課題が可視化される
中期経営計画を作成する過程では、必ず自社の現状分析を行う必要があります。過去3年間の決算書や営業実績、市場での競争環境をデータとして集め、分析するのです。
この作業を通じて、普段は見落としていた経営課題が浮かび上がってきます。製造プロセスに非効率な部分がないか、人員配置は最適か、商品開発のスピードは競合と比べて遅くないかなど、多くの気付きが生まれるのです。課題の見える化こそが、改善への第一歩になります。
従業員のモチベーション向上と目標共有
従業員は、自分がしている仕事が企業全体の成長にどう貢献しているのかを理解したいと考えています。中期経営計画があると、その質問に対して明確な答えが返せるようになります。
営業部門の売上目標が企業全体のビジョンとどのようにつながるのか、製造部門の品質向上がどのような価値を生むのか、こうしたことが明確になると、社員の仕事に対する充実感が高まるのです。結果として、組織全体のエンゲージメントが向上し、個々の業務成果にもプラスの影響が出ます。
経営資源の最適配分が実現される
企業には限られた「ヒト」「カネ」「モノ」という資源があります。中期経営計画があると、これらをどの事業に、どの程度配分すればよいかが明確になるのです。
優先度の高い事業には人材を集中させ、成熟期にある事業からはリソースを減らすといった戦略的な判断が可能になります。このように資源を最適配分することで、限られた予算の中でも最大の成果を生み出せるようになるのです。
市場変化への対応力が強化される
中期経営計画を策定する際には、外部環境の分析が必ず含まれます。競合企業の動き、業界全体のトレンド、テクノロジーの進化など、自社に影響を与える要因をあらかじめ想定しておくのです。
こうした分析を行うことで、市場で何か予期しない出来事が起きたときも、あらかじめ用意した対応策から選択肢を見出すことができます。完全に予測できなくても、「もし〇〇になったら、△△という対応をしよう」という心の準備ができているだけで、対応スピードが大きく変わるのです。
中期経営計画策定前の準備と体制
中期経営計画の質を高めるためには、策定前の準備がとても重要です。
体制構築と役割分担
大規模な企業では、経営トップと経営企画部が中心となって策定するのが一般的です。ただし、最近では組織全体の力を活用するために、各事業部門の責任者や次世代リーダーなども巻き込んで、ワークショップ形式で進める企業が増えています。
重要なのは、経営層のビジョンを具体化するだけでなく、現場の知見も計画に反映させることです。事業ごと、部署ごとに担当者を決め、それぞれのレベルでの検討を並行して進めることで、より実行性の高い計画が生まれるのです。
必要なデータの収集と分析
中期経営計画の策定には、膨大な過去データが必要になります。
- 過去3年間の損益計算書や経営成績
- 顧客別、商品別の売上明細
- 競合企業の市場シェアと経営戦略
- 業界全体のトレンドと市場規模
- 自社従業員の人員構成とスキル分析
- サプライチェーンと仕入先の情報
- 技術動向と業界規制の予測
これらのデータを早期に整理しておくことで、後々の分析作業がスムーズに進みます。
スケジュール調整と進行管理
複数の部門が関わる大きなプロジェクトなので、スケジュール管理が非常に重要になります。各部署からのデータ提出の期限、ワークショップの開催日時、レビュー会議の予定など、細かく調整しておく必要があります。
一つの遅延が全体のタイムラインに影響するので、早めに担当者間で共有し、進捗状況を定期的に確認することが大切です。
中期経営計画の作成手順(5つのステップ)
それでは、実際に中期経営計画をどのように作成するのか、手順を説明します。
ステップ1 経営理念の再確認と明確化
最初のステップは、自社の経営理念をもう一度見つめ直すことです。中期経営計画は、この経営理念を実現するための具体的な行動計画ですから、ここが揺らいでいると計画全体の軸がぶれてしまいます。
経営理念には、企業の使命、ビジョン、経営姿勢、価値観という4つの要素が含まれます。10年後、20年後に目指す理想像があるなら、そこから逆算して3~5年の道筋を描くことが可能になるのです。経営理念が明確に可視化されていれば、中期経営計画作成時に判断に迷う場面でも、一貫性を保ちやすくなります。
ステップ2 現状分析と外部環境の把握
次に、自社の現状がどうなっているのかを徹底的に分析します。財務面では過去の売上推移、利益率、キャッシュフローの状況を見ます。営業面では顧客の属性、商品別の成績、営業活動の効率を調べるのです。
同時に外部環境も分析する必要があります。PEST分析を使って、政治・経済・社会・技術の観点から、業界全体の環境を把握するのです。競合企業は何をしているのか、市場全体は成長しているのか縮小しているのか、新しいテクノロジーは自社に脅威か機会かといった点を整理します。
ステップ3 経営戦略の決定と将来ビジョン設定
現状分析が終わったら、いよいよ経営戦略を決定します。SWOT分析を活用して、自社の強み、弱み、機会、脅威を明らかにし、どこで勝負するのかを決めるのです。
強みをさらに伸ばす戦略もあれば、弱みをカバーする戦略もあります。外部環境から生まれた機会を生かす戦略や、脅威を最小化する戦略も考えます。これらを組み合わせて、3~5年後の企業のあるべき姿、つまり中期ビジョンを設定するのです。
ステップ4 数値目標と行動計画の設定
戦略が決まったら、それを実現するための具体的な数値目標を設定します。売上目標をいくらにするのか、利益率をどこまで高めるのか、顧客満足度はどの程度にするのかといった目標を決めるのです。
数値目標を設定する際は、最終的に達成したいゴールから逆算して、途中に通過すべき小さなマイルストーンを決めるのが効果的です。そして各事業部単位で、その目標を実現するための具体的な行動計画を立てるのです。営業戦略、商品開発計画、組織改革、人材投資など、多くの施策が含まれることになります。
ステップ5 複数シナリオの作成と最適化
最後のステップは、作成した計画が本当に実現可能なのかを検証することです。一つの計画だけでなく、複数のシナリオを作成するのが効果的です。
例えば、「経済が好調に推移するケース」「経済が停滞するケース」「新しい競合が参入するケース」など、異なる状況を想定した複数の計画を用意しておくのです。そのうえで、どのシナリオでも実行可能な部分と、シナリオによって対応を変える部分を整理することで、より堅牢な計画が完成するのです。
中期経営計画に含めるべき分析フレームワーク
中期経営計画を策定する際に活用される、いくつかのフレームワークがあります。
SWOT分析による内外環境の把握
SWOT分析は、企業の強み(Strengths)、弱み(Weaknesses)、機会(Opportunities)、脅威(Threats)を整理するツールです。
強みと弱みは企業内部の要因で、自社がコントロール可能なものです。機会と脅威は企業外部の環境要因で、自社でコントロールできないものです。このマトリクスを埋めることで、戦略的にどこに注力すべきか、どこでリスク管理が必要かが見えてくるのです。
PEST分析による外部要因の評価
PEST分析は、企業を取り巻く外部環境を、政治(Political)、経済(Economic)、社会(Social)、技術(Technological)の4つの観点から評価するフレームワークです。
政治的な規制の変化、経済の景気サイクル、社会的価値観の変化、新しい技術の登場など、様々な外部要因が事業に影響を与えます。これらを体系的に整理することで、中期経営計画に盛り込むべきリスク対応策が明確になるのです。
3C分析による戦略立案
3C分析とは、顧客(Customer)、競合(Competitor)、自社(Company)という3つの視点から、ビジネス環境を分析するフレームワークです。
顧客は何を求めているのか、競合はどのような強みを持っているのか、自社はそこでどのような価値を提供できるのか。この三つの要素を組み合わせることで、差別化できるポジショニングが見えてくるのです。
事業戦略と組織・人事戦略の連動
近年では、事業戦略の強化と同じくらい、組織戦略や人事戦略が重要視されるようになってきました。従来は採用や配置転換は事務的に行われていましたが、今では事業戦略の実現に必要な人材を計画的に育成・配置することが求められるのです。
事業戦略で定めた新規事業の立ち上げには、どのような人材が何人必要か。既存事業の効率化には、どのようなスキルの人材を集めるべきか。こうした点を事業戦略と連動させて考える必要があるのです。
中期経営計画の具体的な内容構成
中期経営計画に何を書き込むのか、その内容についても説明します。
定量的な数値目標の設定
中期経営計画には、必ず数字が含まれます。売上高、営業利益、営業利益率、ROE、顧客数など、企業が重視する経営指標をすべて数値化するのです。
これらの数値目標は、現在の状況から見て挑戦的でありながらも、実現可能な水準に設定することが大切です。現実離れした目標では、従業員のやる気を失わせてしまいますし、逆に低すぎる目標では企業の成長につながりません。過去のトレンドと市場環境を慎重に検討して、適切な水準を決めるのです。
定性的な戦略と施策の記載
数値目標を達成するためには、どのような戦略を取るのか、具体的な施策は何かを記載する必要があります。例えば「新商品開発に注力する」という戦略なら、具体的にはどのような商品を、いつまでに開発するのか、どの程度の投資をするのかという情報が必要です。
組織改革、人材育成、デジタル化推進、顧客サービスの向上など、多様な施策が中期経営計画に含まれることになります。これらが数値目標とどのように結びついているかを明確にすることで、計画全体の一貫性が保たれるのです。
財務目標と非財務目標のバランス
かつては、中期経営計画といえば財務目標、すなわち売上や利益を最大化することだけに焦点が当たっていました。しかし今日では、非財務目標も同じくらい重要になってきています。
顧客満足度、従業員エンゲージメント、ブランド認知度、イノベーション創出の件数、などといった指標です。これらは直接的には利益に結びつかないかもしれませんが、長期的な企業価値向上には欠かせない要素なのです。特にESG投資の拡大に伴い、社会貢献度や環境配慮といった指標も重視されるようになっています。
KPI設定と進捗管理指標
中期経営計画を実行する過程では、進捗状況を定期的にチェックする必要があります。そのために、KPI(Key Performance Indicator)という重要業績評価指標を設定するのです。
例えば、「売上を5年で2倍にする」という目標があるなら、「1年目は125%、2年目は150%」といった中間目標をKPIとして設定します。月次や四半期ごとにこのKPIと実績を比較することで、計画がオンコース(予定通り)なのか、それとも修正が必要なのかが判断できるようになるのです。
中期経営計画の実行と浸透のポイント
中期経営計画がいかに素晴らしくても、組織全体で実行されなければ意味がありません。計画を実行に移し、組織全体に浸透させることは、策定と同じくらい重要なプロセスです。
全社への共有と理解促進
計画が完成したら、まずは全社員に対して、計画の内容と意義を丁寧に説明する必要があります。経営層が企業の将来像を一方的に押しつけるのではなく、社員に対して「なぜこの方向に進むのか」「自分たちはどう貢献するのか」を理解させることが大切です。
説明会の開催、社内報での発信、オンライン動画での配信など、複数のチャネルを使って、繰り返し情報を発信することが効果的です。特に大企業では、すべての社員が計画の存在を知ること自体が困難ですので、工夫が必要なのです。
組織レベルでの目標設定
全社的な目標が定まったら、次は各部門・各チームレベルでの目標を設定します。営業部は売上目標いくら、製造部は原価削減いくら、といった具合です。
この段階で重要なのは、上から与えられた目標ではなく、各チームが納得した目標にすることです。現場の意見を取り入れながら、全社目標を各部門で分解していくプロセスを通じて、初めて各チームが当事者意識を持つようになるのです。
個人のタスクレベルへの落とし込み
最終的には、中期経営計画が個々の従業員の日々の仕事に落とし込まれる必要があります。「営業チーム全体として売上を100万円増やす」という目標があるなら、営業担当者一人ひとりは「あなたは月30万円の追加売上を目指してください」という具体的なタスクに変換される必要があります。
「来月は新規顧客を5件開拓し、既存顧客から10件の追加受注を取ること」というように、個人レベルでの行動が明確になれば、中期経営計画は初めて実行力を持つようになるのです。
予実管理と進捗モニタリング
計画の実行を開始したら、定期的に予定と実績を比較する「予実管理」が必須です。予定通りに進んでいるのか、それとも遅れが生じているのかを把握し、必要に応じて軌道修正する必要があります。
月次で、または四半期ごとに、KPIの達成状況を確認し、経営層に報告します。もし遅れが見られたら、早めに対応策を検討し、実行することで、計画全体の達成可能性を高めるのです。
中期経営計画策定における注意点
中期経営計画は多くの企業で活用されていますが、陥りやすい落とし穴もあります。
計画倒れを防ぐための工夫
中期経営計画を策定したはいいが、その後の実行が伴わないというケースは少なくありません。計画が計画のまま、実行されない「計画倒れ」に陥ってしまうのです。
これを防ぐためには、経営層が先頭に立って、継続的に計画の進捗を確認し、全社に発信することが大切です。また、計画の実行状況を人事評価に反映させるなど、組織全体で計画実行への意識を高める工夫も必要です。計画は「作ったら完成」ではなく「作ってから本当の仕事が始まる」というマインドセットを浸透させることが重要なのです。
現実と乖離した目標設定を避ける
企業の経営層は、どうしても野心的な目標を掲げたいという心理が働きます。しかし、実現不可能な目標は、従業員のやる気を失わせるだけです。
現実的には実現可能でありながらも、挑戦的な目標を設定することが大切です。そのためには、過去のデータを十分に分析し、市場環境を正確に把握したうえで、目標を決めることが不可欠です。野心と現実のバランスを取ることが、中期経営計画の質を大きく左右するのです。
環境変化への対応と柔軟性の確保
3~5年という期間があっても、世の中は予想外に変わることがあります。新しい競合企業が参入するかもしれませんし、技術革新が急速に進むかもしれません。経済環境が大きく悪化することもあります。
中期経営計画は立てたら変えてはいけないものではなく、環境の変化に応じて柔軟に修正されるべきものです。少なくとも年1回の見直し時期には、計画の前提となる仮説が今も成り立つのかを確認し、必要があれば内容を改めるべきです。
リスクシナリオと対応策の事前準備
予期しない出来事への対応能力を高めるには、あらかじめリスクシナリオを想定し、対応策を用意しておくことが有効です。
例えば、為替変動のリスク、資材価格の高騰、主要顧客の喪失、主要人材の離職、といった様々なリスクを洗い出し、「もし〇〇が起きたら、△△という対応をする」という対応策を事前に用意しておくのです。完全には予測できない未来に対しても、こうした事前準備があるだけで、対応スピードや組織の混乱度合いが大きく変わるのです。
中期経営計画の見直しと運用管理
中期経営計画の策定は終わりではなく、その後の継続的な見直しと運用管理こそが、計画の価値を実現するうえで決定的に重要です。
年1回以上の見直しサイクル
最低でも年に1回以上、中期経営計画の見直しを行うべきとされています。この時点で、実績と計画のギャップを分析し、その原因が何であったのかを探ります。
市場環境の変化が原因なのか、それとも組織の実行力が不足していたのか、あるいは当初の計画の前提そのものが間違っていたのかによって、対応が変わります。原因を正確に把握することで、その後の施策の精度が高まるのです。
ローリング方式による継続的更新
多くの企業では「ローリング方式」で計画を更新しています。これは、毎期の見直し時に、新しい1年を計画期間に加えることで、常に3年または5年先までの計画を保有するようにする方法です。
例えば、2024年の計画が2024年~2026年だったとすると、2025年の見直し時に2025年~2027年に更新し、さらに2026年の見直し時に2026年~2028年に更新するということです。こうすることで、常に一定期間先までの計画を持ち続けることができるのです。
長期ビジョンとの整合性確認
見直しの際には、現在の中期経営計画が長期経営計画と整合しているかも確認する必要があります。外部環境の大きな変化があると、中期計画を修正したのに、長期ビジョンと矛盾してしまうケースが起きることがあります。
中期的な軌道修正と長期的なビジョンのギャップを検出し、必要があれば長期経営計画も修正するという、柔軟な対応が求められるのです。短期的な修正と長期的な一貫性のバランスを取ることが、企業の持続的成長につながるのです。
中期経営計画策定における近年の傾向と課題
経営環境の急速な変化に伴い、中期経営計画の策定方法や内容にも、いくつかの新しい傾向が生まれています。
人材戦略の重要性の高まり
これまで中期経営計画の中心は、事業戦略と財務計画でした。しかし近年、人材の獲得や育成がビジネスの成功を左右する要因として認識されるようになってきました。
優秀な人材を確保できるかどうか、既存社員のスキルをどのように高めるか、組織文化をどのように構築するか。こうした人事・組織戦略が、事業戦略と同等の重みを持つようになっているのです。伸びている企業ほど、中期経営計画の中で人材戦略に大きなスペースを割いているという傾向が見られます。
未来洞察と成長領域の探索
従来の中期経営計画は、過去のデータを基にした延長線上で戦略を立てることが多くありました。しかし、VUCAの時代(不確実性、複雑性が高い時代)では、過去の延長では対応できないような変化が起きています。
最近では、未来がどのように変わるかを深く思考し、その中から新たな成長領域を探索するアプローチが注目されています。単に過去のトレンドを分析するのではなく、5年後の社会はどうなっているのか、そこでの顧客ニーズは何か、という視点から戦略を構築するのです。
シナリオ分析とボラティリティ対応
不確実性が高い時代だからこそ、複数のシナリオを想定し、それぞれへの対応策を用意する「シナリオ分析」の重要性が高まっています。
為替変動、資材価格の変動、新しい競合の参入、需要減など、様々なボラティリティ(不安定要因)に対し、企業がどのように対応するかを事前に定めておくことで、実際に変化が起きた時の対応力が飛躍的に高まるのです。
ESG・SDGsの組み込み
従来の中期経営計画は、経済的な利益追求に偏っていました。しかし今日では、企業の社会的責任、環境への配慮、ガバナンス(ESG)や持続可能な開発目標(SDGs)への対応が、ビジネス戦略と同じくらい重要になってきました。
単なるCSR活動ではなく、企業の本業の中でいかにESG・SDGsに貢献するかを中期経営計画に組み込む企業が増えています。このアプローチにより、企業の長期的な価値向上と社会への貢献が両立するようになるのです。
中期経営計画の成功事例に学ぶポイント
中期経営計画を有効に活用している企業には、いくつかの共通点があります。
経営メッセージの明確化
成功している企業の中期経営計画には、必ず経営層からのメッセージが込められています。単なるデータと数字の羅列ではなく、「なぜこの方向に進むのか」「企業が社会に対して何を実現したいのか」という想いが伝わってくるのです。
このメッセージが明確だと、社員が計画を読んで納得しやすくなり、自分たちのタスクとの結びつきが理解しやすくなります。結果として、計画の実行力が格段に高まるのです。
読み手(ターゲット)の想定
中期経営計画を読むのは、経営層だけではありません。従業員、取引先、金融機関、投資家など、多くのステークホルダーが計画を読みます。
成功している企業は、異なるターゲット層に対して、どのようなメッセージを、どの程度の詳しさで提示するかを意識して計画を作成しています。従業員向けには行動指針を中心に、投資家向けには財務見通しを詳しく、といった具合に、読み手に応じた情報の強調点を変えているのです。
数字とストーリーの連動
最後に重要なのは、単なる数値目標ではなく、その背景にあるストーリーが明確になっていることです。「売上を5年で2倍にする」という数字があるなら、その背景に「新商品の立ち上げ」「海外市場への進出」「既存顧客との関係深化」といった具体的なストーリーがあるのです。
このストーリーが明確だと、経営層から現場の従業員まで、すべてのレベルで理解と納得が深まります。また、予期しない状況が起きたときも、ストーリーに基づいた柔軟な対応が可能になるのです。
まとめ
中期経営計画の策定は、企業の継続的な成長と発展のための必須のプロセスです。3~5年という適切な時間軸で、経営理念から具体的な行動計画まで、階層的に思考を深めていくことで、組織全体の意思統一と実行力が生まれるのです。
計画を策定することと同じくらい、その後の実行と見直しが重要です。環境の変化に応じた柔軟な修正と、継続的な進捗管理を通じて、初めて計画が価値を発揮するようになります。さらに、人材戦略やESG対応といった近年の課題も視野に入れながら、時代に即した計画を作成することが、これからの企業競争力を左右するでしょう。